高揚系グルーヴィーソフトロックとして人気の”The Jet Song (When The Weekend’s Over)”で知られるThe Groop。まず、その最高の一曲を聴きましょう。
彼らの唯一のアルバムは恐ろしくレアであるため私は残念ながらLPを持っていない。
”The Jet Song”の7インチ1枚と2007年にSundazed Musicより出されたCDしか持っていないので記事を書くのをためらっていたが、前回The Carnivalの記事の中でThe Groopとの相似性を語っており、無理矢理であるがセルメンと全く関係が無いわけでもないのでこれを機会に記事にさせていただく。よろしくお付き合いのほどを。
なお、当記事の情報源はもっぱらKeith D’ArcyによるCDのライナーノーツと当時の音楽誌からのものである。オリジナル盤に記載の情報は得られなかったことをお断りしておく。
The Groopとはどんなバンドか?
The Groopとは1969年に数ヶ月だけ存在した男性2人女性2人の混声コーラス・グループだ。Mamas & Papas直系のフォークロックとThe Fifth Dimensionのグルーヴィーさを共存させたようなソフトロックグループである。
メンバーは以下の4人。
Susan Musmanno (F.Vocal)
Brian Griffiths(M.Vocal)
Corlynn Hanney (F.Vocal)
Richard Caruso(M.Vocal)

後述の経緯によりA&Mの元プロデューサーRichard Adlerにより結成されBones Howe配下のプロデューサーであるToxey Frenchの指揮の下、Wrecking Crewの面々がバックを務めるという同時期のThe Carnivalとほぼ同じ環境でアルバムが作られた。
The Groopが幸運だったのはToxey FrenchがJohn Barryから映画”Midnight Cowboy”(邦題「真夜中のカーボーイ」)』の挿入歌の提供を求められ2曲がサントラ盤に収められたこと。
1969年4月から5月にかけてアルバム収録曲のレコーディングが完了。6月には1stシングル” A Famous Myth / Tears And Joy”(Bell Records – B800)がリリース。 “映画”Midnight Cowboy”も好評で、John Barryの縁もあって8月から2ヶ月のスペインツアーを敢行。
ショーは好評であったが、Susanが途中急性虫垂炎で入院、残りメンバーでツアー続けたがメンバーのストレスと音楽の方向性の違いによりツアー終了時にはバラバラになってしまいここで事実上解散状態になった。
この間に2ndシングル”The Jet Song (When The Weekend’s Over) / Nobody At All” (Bell Records – B822)がリリース。Billboardのアダルト・コンテンポラリー部門で10月から11月にかけてチャートインし最高35位まで行ったものの、この時既に活動は停止しておりリリースされるはずのアルバムも有耶無耶に。
私が記事を書く時に参照しているBillboard誌、Cash Box誌、Record World誌のいずれにもアルバムがリリースされたという情報が見つからなかった。ネット上の情報によれば90年代になってどこからか未開封盤が発掘されて注目を集めるようになったとのこと。
この10年間ヤフオクでもeBayでも出品歴はなく、2011年にディスクユニオンの廃盤アナログセール情報に掲載されたくらいの情報しかない。多分出てもすごい高値がついて私は結局買えないと思う。でも持っている人は持っているんだろうなと羨ましく思う。
一方、シングル盤はいずれも手頃な価格で出回っており私の周囲でも持っている人は多い。
収録曲について
アルバムの収録曲を紹介する。(曲名にSpotifyのリンクを貼っておくので実際に聴いていただきたい。)
A1 A Famous Myth (Jeffrey Comanor)
映画”Midnight Cowboy”(邦題「真夜中のカーボーイ」)』の挿入歌として作られた曲。ドリーミーでメランコリックバラード。美しいハーモニー。
A2 I Try To Think Of You When I Can (Ed Millis)
Ed Mills はThe Jet Songを作曲したChris Duceyの共同制作者でこのアルバムで2曲を提供。The Groopの音楽性はThe Fifth DimensionとMamas & Papasの影響下にあると言われているが、この曲はまさにローレルキャニオン直系のフォーク・ロックでMamas & Papasフォロワーらしい佳作。
A3 The Continental ( Con Conrad, Herbert Magidson)
懐かしい感じの曲。というか本当に古い曲で、このオリジナルは音楽関係の賞が追加された1934年の第7回アカデミー賞で最初の歌曲賞を受賞した作品。フレッド・アステアとジンジャー・ロジャースのコンビによる初主演作”The Gay Devorce”(邦題「コンチネンタル(離婚協奏曲))。古い曲なので懐かしさを感じるのは当然だがあえてこの曲を選んだところHarpers Bizarreの影響を感じる。
A4 Blustery Day (Ed Millis)
静かなイントロなのでデジタル時代のリスナーは聴き飛ばしてしまうかもしれないがMamas & Papasばりのメリハリの効いた迫力がありかつ美しいハーモニーが魅力の佳作。私の個人的な好みではこのアルバムの中で上位に入る作品。
A5 Goin’ Back (Goffin and King)
Carole KingとGerry Goffin元夫妻の作によるものでDusty Springfieldのバージョンが最も売れたがThe Byrdsのものもよく知られている。というかDavid CrosbyがThe Byrdsを去る原因にもなった曲。ここでは“Sneaky” Pete Kleinowによるペダルスティールが効果的に使われているがDave Grusinのホーンアレンジがカントリーっぽさを消している。
A6 Time Fire (Jeffrey Comanor)
これもMamas & Papasフォロワーらしさが出た短調の佳作。
B1 The Jet Song (When The Weekend’s Over) ( Chris Ducey)
みんながノックアウトされたこのアルバムのハイライト。Mike Nesmith絡みの幻のバンドThe Penny ArkadeのChris Ducey作の高揚感溢れる”Up, Up and Away” 路線の曲。私はいつも2回目の上昇の後に、ロジャニコの”Love So Fine”をぶっこむというベタな繋ぎをしつこくしているくらい大好きな曲である。間違って1回目の上昇の後にカットインすると大切なパパパコーラスが無くなるので要注意。このパパパコーラスによってもたらされる多幸感は最高で、ベタと言われようがかけてしまえばこっちのものでみんなが幸せな気分になる名曲。
B2 Nobody At All (Jeffrey Comanor)
先行シングル発売されたThe Jet Song (When The Weekend’s Over)のフリップサイドに採用された曲。一転してしっとりとした曲調だが複雑に絡み合う美しいハーモニーのソフトロック。
B3 Haunted Places (Jeffrey Comanor)
これもComanorの曲だが、タイトルは「心霊スポット」という意味でアルバムの中でアクセントをつけるために選ばれたのだろう。いろいろと恐そうな効果音がイントロで使われているが、これもMamas & Papas直系のフォークロック路線の佳作。
B4 Just Don’t Know How To Say Goodbye ( Joey Stec, Sandy Salisbury )
The MillenniumのJoey Stec, Sandy Salisburyによる作品でThe Millenniumの作品としては当初リリースされず2003年にリリースされた未発音源曲集”Pieces”で世に出たもの。彼ららしい優しく美しいハーモニーで素晴らしい。
B5 Wonder Why ( Chris Ducey)
The Jet SongのChris Duceyによる曲。The Fifth Dimensionライクなハーモニーとサビのベースラインがカッコいい。
B6 Dianny, Help Me Now (Jeffrey Comanor)
ベースのルート弾き(Joe Osboneか)に乗せた静かな前半から徐々に盛り上がるハーモニー、アルバムのラストを飾るに相応しい佳曲。
このアルバムで5曲、映画”Midnight Cowboy”のサントラで使われた” Tears And Joys”も含めれば6曲を提供したJeffrey Comanorは、England Dan & John Ford Coleyがカバーし1978年Billboard Hot 100で9位、US Adult Contemporary (Billboard)では1位になったAORの名曲”We’ll Never Have to Say Goodbye Again”の作曲者。当時新進気鋭のソングライターとしてBones Howeのお抱えだったようだ。
アルバムには収録されていないCD再発時ボーナストラックについても触れておく。
#1 Tears And Joys (Jeffrey Comanor)
こちらも「真夜中のカーボーイ」のサントラに採用された曲。グルーヴィーなベースラインが良いファンキーな曲。
#2 Don’t Leave Me (Harry Nilsson)
Harry Nilssonの2ndアルバム”Aerial Ballet”に収録された曲のカバー。これはThe Groopが事実上解散した後の12月にMike BernikerとPhil RamoneのプロデュースでSusanとセッションシンガーのMichaelによって録音されたものでもはやThe Groopとは別物。新生Groopを企図したものだったようだが後が続かず未発表のままお蔵入りとなった。メンフィスソウルっぽいギターイントロからTower of Powerを想起する重厚なホーンアレンジ、縦横無尽に走るベースラインなど完成度は高い佳作だが南カリフォルニアの音ではなくなっている。詳細は知らないがDave Grusinのアレンジではないと思う。
[Credits]
Bass – Joe Osborne, Jerry Sceff
Drums – Jim Gordon
Electric Piano – Pete Jolly
Guitar – Ben Benay, Dennis Budimir, Mike Deasy, Tom Tedesco
Pedal Steel – “Sneaky” Pete Kleinow
Percussion – , Larry Bunker
Keyboards – Larry Knechtel, Mike Melvoin
String and Horn Arrangement – Dave Grusin
Vocal Arrangement – The Groop
Producer – Toxey French
なお、手元の資料では確認できなかったがロジャニコの”DON’T TAKE YOUR TIME”のアレンジをしたBob Thompsonもアレンジャーとして参加している模様。オリジナルのアナログ盤にクレジットが記載されているかもしれないのでお持ちの方がいたら是非教えて頂きたい。
音楽誌の評価
短期間で解散してしまいレーベルとしても宣伝広告する以前だったのであまり記事は見つけることはできなかった。シングルリリース時に以下の記述がある。
THE GROOP (Bell 800) A Famous Myth (3:22) (Mr. Bones, BMI – Comanor) From the score of “Midnight Cowboy,” this brilliant soft -splendor ballad presents powerful evidence of the movie’s musical impact. Group (or Groop features a sound in the vein of Mercy or early Mamas & Papas (“California Dreaming”) for exceptional across -pop -lines runaways. Flip: No info available.
June 14,1969 Cash Box
Sleepr Picks of the week
The Groop, who take after the Mamas and the Papas, are featured singing “A Famous Myth” (Mr. Bones, PM)) in “Midnight Cowboy” (Bell 800).
June 14,1969 Record world
両誌ともMamas&Papas路線と評している。ちなみにRecord World誌のSleeper Picks of the weekとは「今週の注目株」といった意味。
GROOP -The Jet Song (When the Weekend’s Over) (Prod. Toxey French) (Writer: Ducey) (Sufi Pipkin, BMI)-Good new group sound with an easy rhythm entry, much in the “Up, Up and Away’”vein is sure to garner much airplay and sales. Bell 822
Sep. 6, 1969, BILLBOARD
The Jet Songについてはやはり”Up, Up and Awy”路線と評し、今後のオンエアと売上に期待を寄せている好意的な評価。
グループ結成の経緯①Sergio Mendes & Brasil ‘66のボーカリストへの誘い
CDのライナーノーツによればこうだ。まず、Sergio Mendes & Brasil ‘66のマネージャーであったRichard Adlerが1968年にセルメンと一緒にワシントンD.C.でウエスト・サイド物語の地方公演を観た際、ブルネットの素敵な女性に目をつけたことが始まりだ。その女性こそ当時19歳のSusan MusmannoでAdlerは彼女の存在感と歌唱力を評価し、Brasil ‘66に誘い、セルメンも交えて面談しLAまでオーディションを受けに来るよう誘った。
長年のセルメンファンである私としては、ここでふと疑問に思うことがある。前回のThe Carnivalの記事で触れたようにセルメンは67年末メンバー全員をクビにしてメンバー変更を敢行している。1968年、残留したLani Hallに加えて既に歴代ボーカリストの中でも美人の誉れ高いKaren Philipp(TV版M*A*S*HではMaggie少尉役に出演するため72年に脱退)がセカンド・ボーカリストとして在籍しておりAdlerのどんな思惑でSusanを誘ったのであろうか。

女性ボーカル3人体制にするのか、それとも美人の誉れ高い私の大好きなKaren Philippをクビにするつもりだったのか?もしクビにしていたら90年代にセルメン再評価のきっかけとなった”For What It’s Worth”の歌声を聴けなかったことになる。
Richard Adlerは元々A&Mのプロデューサーで、セルメンに女性ボーカルをフィーチャーしたポップ路線を提案した人物である。ブラジルの軍事政権を忌避してアメリカに渡ったものの公演が好評であったことと裏腹にAtlanticから出したレコードの売上が低迷していたことからセルメンはAdlerの提案を受け入れA&Mと契約した。セルメンとの関係においてそれなりの発言力はあったのであろう。
話がだいぶ脱線したが、提案を受けたSusanは元々ミュージカル女優を目指していたこともあり当初この話を躊躇していた。しかし母親の後押しもありオーディションを受けることを決意。
しかし、いざLAに行ってみるとRichard Adlerはセルメンの下を離れて新たなプロジェクトを計画していた。
グループ結成の経緯②Richard Adlerの野望
Richard Adlerは究極のポップグループを作ることを計画していたがその中心にSusan Musmannoを据えようとした訳だ。
The Groopの作品を現在の日本のソフトロック好きの人たちが聴くと嫌いな人は殆どいないと思う。それは私たちがおぼろげに持っているソフトロックの共通認識と呼ぶべき要素が全部入りだからだ。職業作曲家による優れたメロディーと美しいハーモーニー、卓越した技術を持つ演奏家、エンジニア、バーバンク風味、ポップなイメージ等々当時考えられる要素を全部組み合わせた究極のグループを目指したのだ。
AdlerはBones Howeにコンタクトを取り、配下のプロデューサーToxey Frenchを紹介され、1968年の夏、Toxey FrenchからはBrian GriffithsとCorlynn Hanneyの紹介を受けた。
カナダ出身のシンガーソングライターCorlynn HanneyとBrian Griffithsと共にCBC(カナダ放送協会)の番組の専属バンドThe Numerality Singersのメンバーとして活躍していた。
Toxey Frenchはドラマーでもあり、The Fifth Dimensionのバックバンドの一員としてバンクーバーに行ったことがありそこでBrianとCorlynnと面識があり、一方、二人はジングル制作の仕事でLAに録音に訪れることも多く互いに会う機会があった。そうした経緯でFrenchは音楽的素養、経験から二人がAdlerのプロジェクトに適任と考え推薦したわけだ。
そして4人目のメンバーとして、Richard Adlerは、行きつけのレストランRed Onionのウエイターで夜は役者をやっているRichard Caruso目をつけた。彼は他の3人より歳が行っていたがある種のカリスマ性があり、すぐにSusanといい仲にななり保守的な環境で育ち当時のLAのユースカルチャーに馴染めないでいたSusanの良きパートナーとなった。
メンバーが決まると4人はHollywoodにあるAdlerの自宅裏のバンガローに集まり、歌とダンスの練習、同時代のポップ・ミュージックの聴き込み等を行いデビューに備えた。
Adlerはこのグループをトータルにプロデュースすることを考えPeta Rimmingtonというスタイリストを雇い流行の最先端の衣装を準備させた。グループの音楽的方向性はMamas & PapasとThe Fifith DImensionを目指したが、ファッション的にはLeft BamkeとHarpers Bizzareの要素を入れた。
ジャケットに採用された4人の写真はAdlerの自宅のリビングで撮影されたものだそうだ。大人しめのヒッピーファッションのようだが映像資料はCDに使われているものが以外見たたことがない。

そして、前述の通り、アルバム制作、映画”Midnight Cowboy*の公開を経て輝かしい未来が約束されたかのように見えたがスペインツアーを機に解散に至った。
その後、アルバムはプレスされカタログナンバーも採番されているが90年代に発掘されるまで市場には出回らなかった模様。制作費もかなりかかっているはずだがグループを維持できないとなれば、流通させ、宣伝広告費をかけてもペイしないという、損切りという経営上の判断だったと推測される。
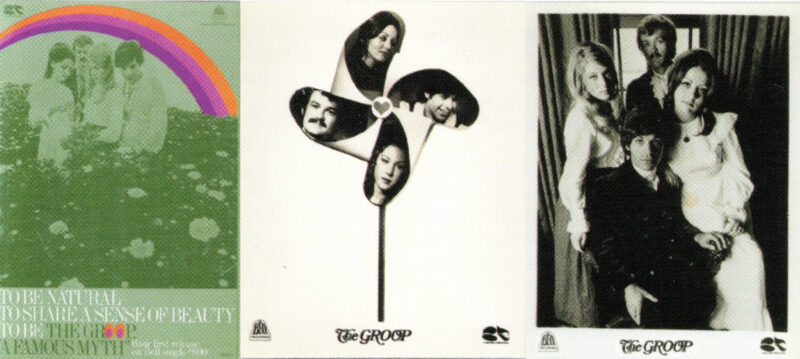
まとめ
一言でいえば、The Groopは野心的なA&R、Richard Adlerによって「つくられたグループ」でBones Productionが全面的に協力しているのだから悪かろうはずがない。幻のアルバムはまさに捨て曲なしの名盤と言っていいだろう。
しかし、メンバーにとっては操り人形のように決められた衣装を着て、強行スケジュールの中で人前で踊りながら歌うことは耐えられなかったのだろう。
同時期の男性2人女性2人の混声コーラス・グループ、The CarnivalはBonesは、同じ Bones ProductionのもとThe Fifth Dimension路線を目指し、1枚のアルバムと3枚のシングルを残した短命バンドということで The Groopと相似性を感じる。
The CarnivalはBrasil ‘66寄りで、The GroopはMamas & Papas寄りという違いはあるが、一番大きな違いは、The Carnivalが運悪く市場に受け入れられなかったのに対し、The Groopはこれから売り出すという時に自らの判断でグループを終焉させたことだ。
その後のメンバーについては以下の通り。
Susan Musmanno
上記の通りグループの自然消滅を受けて新生Groop立ち上げのために1曲録音したがプロジェクトは立ち消えに。カナダを代表する詩人でシンガーソングライターLeonard CohenのバックボーカルをしていたColynnに誘われ同じグループに参加。ここで一緒になったギタリストのElkin “Bubba” Fowlerと結婚し、主にカントリーの分野で音楽活動を続ける。
Corlynn Hanney
グループ解散後すぐにLeonard Cohenのバックボーカルグループに参加。その後もカナダのセッションシンガーとして活躍。カナダの著名な音楽家Miles Ramsayとの間に、一男一女Josh Ramsay と Sara Ramsayがおりともに音楽家として活動している。Corlynnは晩年認知症を患い、2020年12月にCOVID-19のため死去。
Brian Griffiths
既にカナダで商業音楽の実績があったBrian Griffithsは、Brian Gibsonと音楽プロダクション兼広告制作会社Griffiths-Gibson Productions Ltd.を設立。さらにCorlynnの夫Miles Ramsayを加えてLittle Mountain Sound Studiosを設立するなど経営の方に比重を移した。特筆すべきは、「ドラゴンボール」の北米版TV番組のサントラで作詞をしていることだ。私は当時これを息子と観たことがあるが、その時はThe Groopのことなど全く知らなかった。
Richard Caruso
彼については全く情報が見つからなかった。CD再発時の2007年のライナーノーツでも情報なし。
なお、プロデューサーのToxey Frenchは、もともとTommy Roe, Friar TruckなどのアルバムでCurt BoettcherやSandy Salisburyなどと共演したセッションミュージシャンであったが、このアルバムや映画”Midnight Cowboy”のMUSIC PRODUCTIONを務めたことでプロデューサーとしての活躍の場を広めた。特に、1972年にプロデュースとアレンジを担当したThe Free Movement アルバム”I’ve Found Someone Of My Own”はジャンルはソウルながら、Bones Howe一門のソフトロックテイストを感じることができる。興味のある方は是非聴いてみてほしい。
おまけ:映画”Midnight Cowboy”(邦題「真夜中のカーボーイ」)』とThe Groop
映画”Midnight Cowboy”(邦題「真夜中のカーボーイ」)』の音楽といえば、Toots Thielemansの哀愁漂うハーモニカで有名な主題歌”Midnight Cowboy”とHarry Nillsonの”Everybody’s Talkin’” (邦題:「うわさの男」)が有名で映画の中で繰り返し印象的に使われている。
一方、The Groopの曲が映画のどのシーンで使われたか覚えている人は少ないだろう。エンドロールにはちゃんと挿入歌”A Famous Myth”と”Tears And Joys”とともにThe Groopの名前が記されている。
まず、”A Famous Myth”。
テキサスから来た田舎の青年ジョー(Jon Voight)が金持ちの女性をひっかけるの失敗してバーで一人反省会をしているところ話しかけてきた詐欺師の小男ラッツォ(Dustin Hoffman)と意気投合してボックス席で飲んでいるシーンのBGMで使われている。
実は私もこの曲が映画で使われていのを覚えていなかったので今回確認のために何回か観直してようやく見つけた。音が小さいので最初は気づかずにスルーしてしまった。
2曲目、”Tears And Joys”。
こちらも映画の中でどこに使われてか見つけるの苦労した。
終盤、主人公二人が「Warholパーティー」に招待され、会場へ入る前の階段での会話シーンで使われている。パーティー会場から漏れてくる音楽なので音が小さい。注意して聴かないと気づかないだろう。
Keith D’Arcyによれば、サントラ未収録ながらThe Groopはあと2曲、この映画で歌っている。
1曲目は、初めの長距離バスのシーンでジョーのトランジスタラジオから流れてくるWABCというニューヨークのラジオ局のジングル。この段階ではまだニューヨークに希望を抱いている主人公の気持ちにシンクロするようなジングル。
2曲目は、冬の暖房のない廃墟で震えているシーンでラジオから流れてくる”Florida Orange Juice”のCMソング。主人公たちが凍えそうになっている時に無慈悲にも”Orange juice on ice is nice.”などと暢気に韻を踏んでおり、主人公たちは堪らず唯一の財産であるトランジスタラジオを質に入れに行くことになる。
The Groopがこの映画に参加したことは、一般への認知度は別としてJohn Barryの知己を得たことは大きかっただろう。特にToxey Frenchはタイトルロールで”MUSIC PRODUCTION”としてクレジットされており、同時並行で進めたアルバム制作にもプラスに作用したことは想像に難くない。
なお、個人的な話ではあるが私は中学生のときからアメリカンニューシネマにハマっており、この映画は機会があるごとに繰り返し観たお気に入りの作品だ。学生時代、ニューヨークに遊びに行き一人で街をブラブラした時とか、兄に真冬のニューヨークからフロリダに連れて行ってもらった時などこの映画を思い出したものだ。
また、実際にAndy Warholの協力の下撮影されて終盤のパーティーのシーンはいろいろトリビアが隠されていたり、全編に渡り象徴的なシーンが出てくるので興味のある方は特典映像つきのブルーレイを買われることをお勧めする。Amazonでは品切れで中古しか出ていないが参考までにリンクを貼っておく。
以上、脱線が多く長い記事になってしまったが最後まで読んでくださった方がいれば心より御礼申し上げる。次回からはもう少し短めの記事にできるよう頑張りたい。
ご意見等いただけると励みになるのでよろしくお願いします。
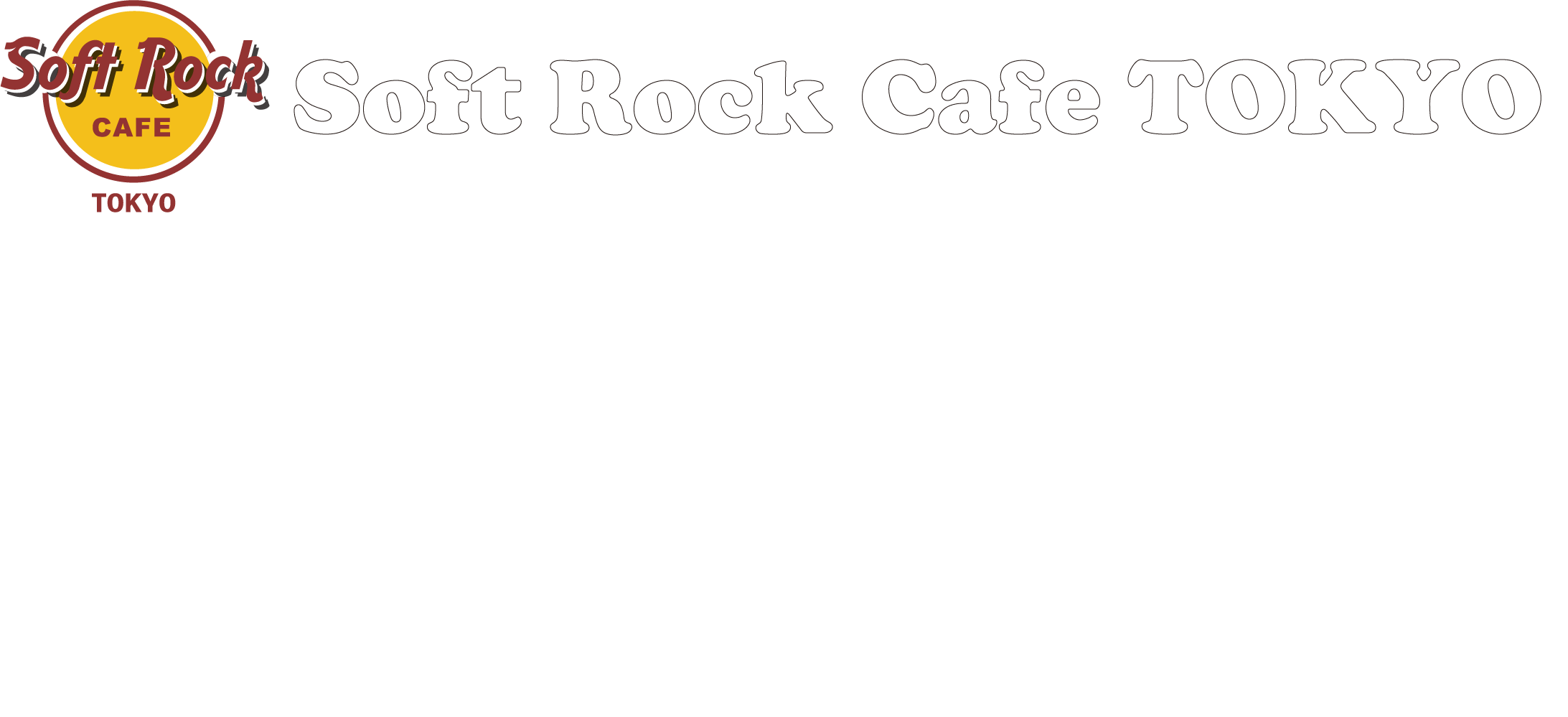



コメント